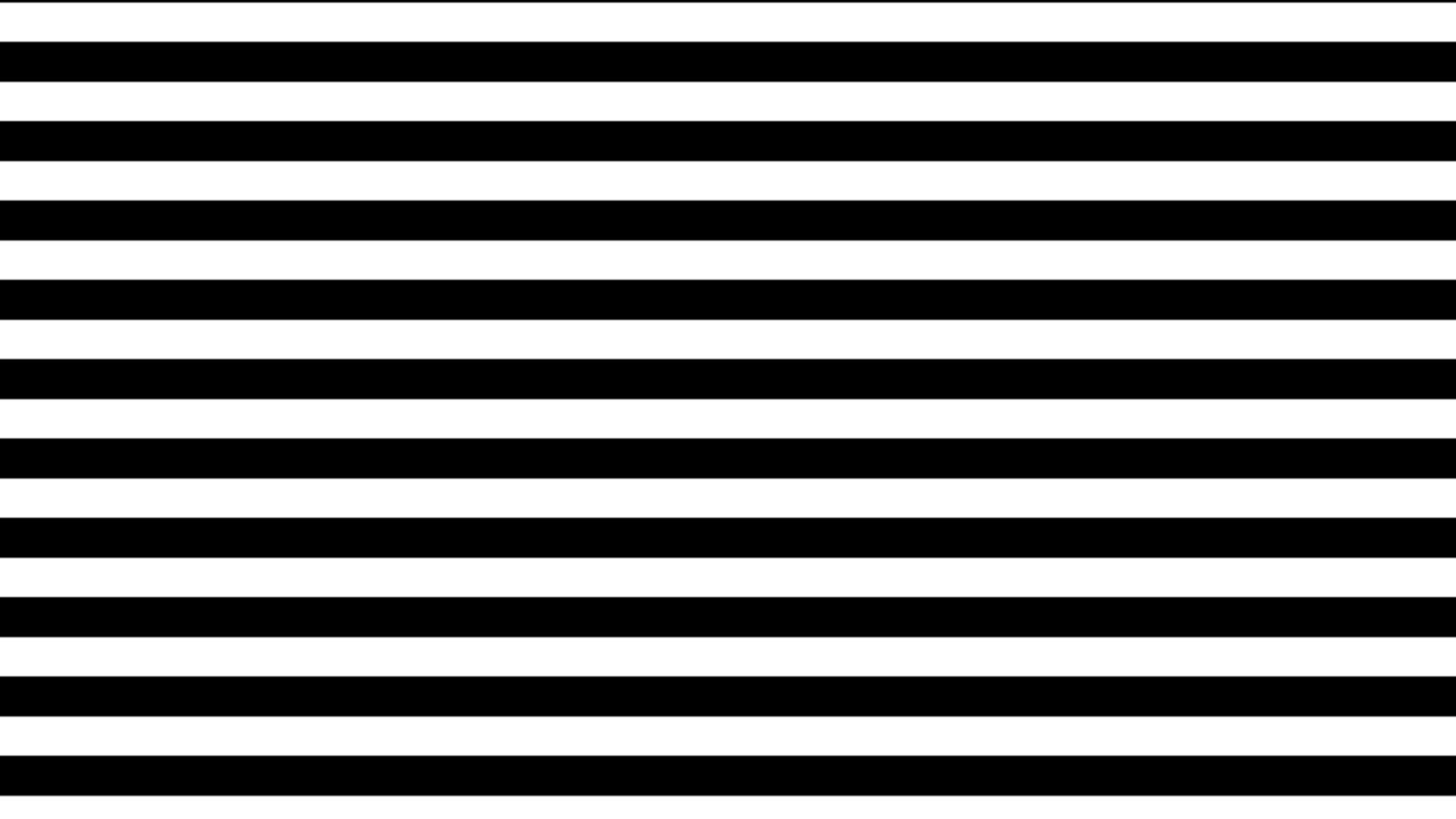他人のラベルに惑わされないために
「ブラック企業」「ホワイト企業」という言葉を、SNSやニュースで目にしない日はありません。けれど、なぜ人はここまで企業を色分けしたがるのでしょうか。
残業が多いからブラック、福利厚生が充実しているからホワイト。そんな評価の物差しは、誰かが外から押し付けているだけではないかと感じることがあります。
私自身、20代の頃は残業時間も気にせず、厳しいフィードバックを浴びながら必死に仕事に取り組んできました。ハラスメントと呼ばれてもおかしくない言葉を浴びた日もありましたが、あの経験が今の仕事の基礎を作ってくれたと心から思っています。だからこそ、その環境を一度も「ブラック」だと思ったことはありませんでした。
「ブラックorホワイト」論争が生まれる理由
ではなぜ、ブラックかホワイトかをめぐる議論が絶えないのでしょうか。SNSやネット記事が注目を集めたいだけなのかもしれません。自分がいる環境は「ブラックではない」と安心したい心理を、上手く突いているようにも見えます。かく言う私も、こうして記事を書いている時点で、その議論に参加してしまっているのかもしれません。
しかし、極端なケースを除けば、仕事に絶対的な「黒」も「白」もないはずです。重要なのは、その環境を自分にとってどう意味づけるか。人間関係、仕事内容、通勤距離、労働時間など評価の軸は人の数だけあり、誰もが違う物差しを持っています。
自分の物差しで働くということ
他人の評価に惑わされず、自分がどう感じているかを軸に環境を測る。それが、働くうえで本当に大切な視点ではないでしょうか。
小さな子どもを見ていると、その感覚がよく分かります。大人が幼稚園をどう評価していようと、本人にとっては先生との関係や友達との遊び、給食が美味しいかどうかがすべて。
周囲の評価より、自分が何を感じているかが一番の基準なのです。
私たち大人も同じです。
外から貼られるラベルに安心や不安を預けるのではなく、自分の心に正直に「今の環境は自分にとってどうか?」と問い続けること。それが、長いキャリアをしなやかに歩むための鍵なのだと思います。
踊らされないために
アクセス数を稼ぐための「ブラックorホワイト」論に、私たちはつい踊らされがちです。けれど、最後に環境を意味づけるのは、あくまで自分。他人の物差しではなく、自分の物差しを持つ。
その姿勢こそが、これからの働き方に必要な強さではないでしょうか。
あなたは今、自分の職場をどんな色で見ていますか。そして、その色を決めているのは誰でしょうか。